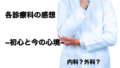こんにちはHikaruです。
編入してからはや5年。いよいよ就職となりました。
(まだ国家試験が残っていますが…)
就活全体の記事などは記録のために残していきたいと思っていますが、今回は端的にマッチングに関して結果と自分なりの考察を述べたいと思います。
初期研修が終了した時、研修期間中に自分がどう思って研修病院を決めたかをある程度振り返られるように書こうと思うので、よければ参考にしてみて下さい。
目次
初期研修で行こうと思っていた病院
何をしたいのか、研修でどういった生活をしたいのか。
病院を選ぶ上で何の判断基準も始めはなく、結構困りましたが、最初に重要視していたことは①救急対応を学べるか、②手技を実践させてくれるかどうか、という点です。
この辺りはあまり一般的な医学生と何の変わりもない志望動機だと思います。
また長く学生をやっていたこともあり、お金や自分の時間がある程度取れるかどうかも重要視していました。
ただ病院見学や病院説明会に参加すると、これが少しずつ変わってきました。
特に自分自身の時間がしっかり取れるかどうか、安心して救急などの症例を学べるかどうか、というところにより注目するようになったからです。
ある病院に見学に行った際、2年目の研修医が1年目を教えている姿を目にしました。
それはさほど珍しい光景ではないのですが、その病院の救急対応が基本的に初期研修医だけで完結しているという話を聞いて「訴えられたりすることって研修医はないのか?研修医だけだと診断ミスなども起きそうだけど。」とふと思いました。
何気なく検索してみると案の定、数年前に病院と研修医が訴えられている判例が出てきました。
背筋が凍るような感覚になったのを覚えています。
「屋根瓦式の指導体制」というと「教え、教えられることで互いに成長していく」とありますが、自分には向いていないのではないかと思いました。
むしろ研修期間中はガッツリ指導医の指導のもと、やり方を学び、一症例ごとにしっかり時間をかけて学んでいける方が良いのではないかと方針を変えました。
そのためにも忙しさに忙殺されるような病院(ハイパー病院)ではなく、どちらかというと自分のペースで研修ができることを謳っている病院(ハイポ病院)で研修し、少しずつ負荷を増やしていくような研修ができればと考えるようになりました。
自分の勉強したいと思っていたこと、忙しさ
先ほどの段落で述べたように、6年生に近づくにつれて研修病院で重要視する項目が変わっていきました。
またマッチングを考えていた時に起きた日赤名古屋第二病院のニュースが大きかったと思います。
これについては初期研修医が悪いのか?上級医に報告し指示を仰ぐことのできないようなシステムが問題ではないのか?など考えましたが、自分の身に降りかかるかも知れない問題としてすごく印象に残りました。
そのため救急ができること、できる限り安心して学べること、将来的な診療科の選択肢を狭めないために幅広い診療科があること、などが大きな決め手になりました。
またこれもはじめに述べたように、自分自身のキャパを超えて働いている研修医や医師が多くいることから、まずはしっかり実力をつけることに集中できるよう、ハイパー病院志向からハイポ病院志向へと変わっていきました。
マッチング登録した病院数
とはいえハイパー病院でも「自分なりにここではやっていけそう」、「それ以外の部分の魅力があるからここで研修するのも良いかも」といった思いもあり、ハイポ&ハイパー含め研修先の候補を三つまで絞りました。
そのうち2つは第一希望者数が例年2-3倍になるような病院だったので、面接の練習といった意味も兼ねてマッチング登録を行う病院をさらに3つ増やし、最終的には6つの病院を登録しました。
この判断に関してはnoteに書こうと思いますが、早めにマッチング対策をしていたこと、病院見学やそれ以外の部分で上位希望の3つの病院に採用してもらえる手応えがあったこと、準備や対策時間などの忙しさも含めて6つにする必要はなかったと思っています。
編入試験の時もそうでしたが、面接に対してはしっかりと対策を立てれば負けることはないと思ったので、もう少し自分を信頼しても良かったかなと思います。
面接対策や病院見学に関しては今回のことでかなり自信がついたので、これもnoteで詳しく書こうと思います。
基本的には3つのうちどの病院を選択しても自分の思いが叶うと考えていたので、最終的に第一希望にする病院は最後まで迷いました。
最終的には自分が将来的に進もうと思っている診療科やその周辺領域に対して理解してもらえ、かつ最も応援してもらえると感じた病院を第一希望にすることにし、無事その病院とマッチすることができました。
私の大学は地方大学なのでやはり地元に残る人たちが大半であり、首都圏や都市部に出ようとする人の方がマイノリティであるため、周りに比べるとかなり早い段階からかなりの労力をかけてマッチングに時間をかけた感はあります。
個人的にも少し時間をかけ過ぎた感はあり、もっと別のことに時間を使っても良かったかなと思う反面、いろんな病院を見ることでどういったところが合うのか、研修医としてここでやっていけそうなのか、何を重視したいのか、どんなメリットを享受できるのか、などを考えて選ぶことはできたかなと思います。
ただ最終的には病院によるものではなく、自分がいかに研修期間を過ごしたいかによると思うので、あんまり病院は関係ないかなという気もしています。
- 初めの思いと見学に行き始めてからの重要視したいポイントは変わった
- 安心して研修できる環境が大事だと思う
- マッチングに早くから時間をかけすぎる必要はない
今回はマッチングについて、簡単に振り返ってみました。
病院説明会や見学などで結局幾つの病院を見たのかざっと数えてみたんですが、少なくとも50-60は見たと思います。
ただあんまり興味のないエリアであったり、初めからそもそも行く気がなかったりするところもあり、しっかり見学に行ったのは1/5程度(10-12病院)だと思います。
見学自体は非常に楽しかったですし、勉強になることもあったので個人的には非常に満足しているんですが、流石にもっと他のことしても良かったんじゃないかとは感じています、、、
あくまでも参考程度に、自分でどんな病院がいいのか、どんなところで働きたいか、初期研修医が病院によってどんな違いがあるのかなど気になる人はたくさん見学に行ってみてもいいかも知れません。
卒業まであと少し、自分の考えを今回のようにまとめるためまた更新したいと思います。
それでは!